- HOME>
- ドクターズインタビュー
院長インタビュー
「最近、なんとなく体が重い」「健康診断で再検査の通知が来たけれど、そのままにしている」──そんな小さな不安が、実は生活習慣病や睡眠障害のサインかもしれません。
京都市にあるおおば内科クリニックは、生活習慣病と睡眠時無呼吸症候群を中心に、一人ひとりのライフスタイルに寄り添った医療を提供する地域密着型のクリニックです。
今回は、同クリニックの院長である大庭 章史 (おおば あきふみ)先生に、医師としての歩みや、患者様との向き合い方、そして治療に込める想いについてお話を伺いました。
医師を志した原点
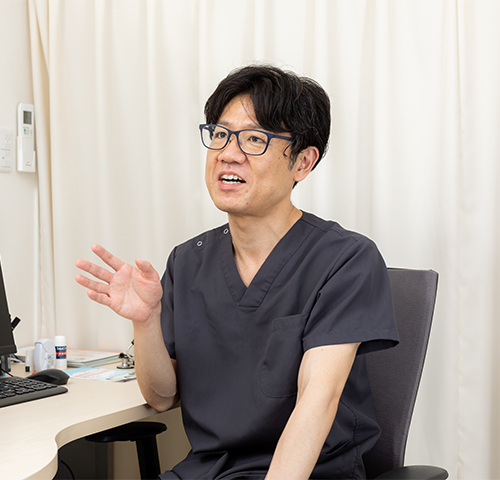
医師を目指すようになったきっかけを教えてください。
医学の道を志したのは、大学生のときです。当初は製薬会社に進もうかと考えていたのですが、学ぶうちに医学の世界に魅了され、もっと深く知りたいという思いが強くなり、医学部へと進みました。
私自身、幼少期に川崎病という病気を患い、定期的に病院へ通っていた経験から、医療には自然と関心がありました。体調管理が必要な中で医療の大切さを身をもって感じていたことも、医師という職業に惹かれた理由のひとつだと思います。お薬の力で多くの人を助けられるかもしれないという発想も当時はありましたが、実際に臨床に触れてみると、患者様と直接向き合うことの面白さや奥深さに強く惹かれました。
人と関わることが好きな自分にとって、医療の現場で患者様と信頼関係を築きながら治療を進めていくというスタイルがしっくりきたのだと思います。今振り返ると、自分の経験と興味が自然とこの道へ導いてくれたのだと感じます。
血液内科を選んだ理由と魅力

血液内科に進まれた理由や、診療でやりがいを感じるのはどんなときですか?
医学部時代から、血液内科に対してはどこか惹かれるものがありました。血液の病気は診断や治療において、データを基にロジカルに進めていく部分が多く、自分の思考スタイルに合っていると感じたのが最初のきっかけです。
とはいえ、一度は「やっぱり違うかもしれない」と迷った時期もありました。実習の中で気持ちが揺らいだこともありましたが、研修医時代に出会った上司の存在や、患者様との密な関係性に魅力を感じ、再び血液内科への気持ちが強まりました。血液の病気というのは、治療が長期にわたることが多く、患者様とはまさに“一生のお付き合い”になることも少なくありません。診察では病気の話だけでなく、家族や趣味の話なども交えながら、人生そのものを一緒に見ていくような時間になります。
また、血液の病気は全身に影響を及ぼすため、身体全体を診る内科医としての力も自然と鍛えられます。そういった意味でも、血液内科での経験は今の自分の基盤になっていると感じています。
地域密着型の診療スタイル
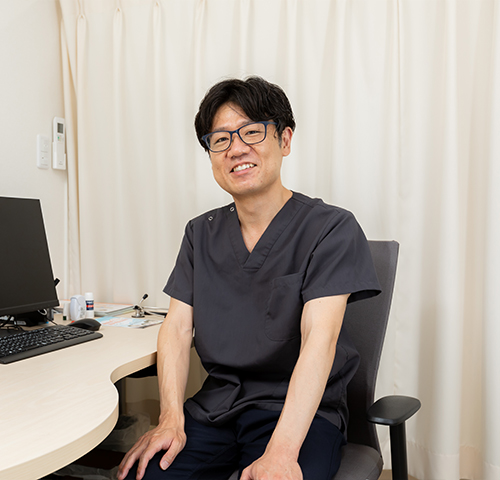
患者様との距離の近さを大切にされている理由は?
私が医療を提供する上で大切にしているのは、「相談しやすさ」や「話しやすさ」です。地域のクリニックという場所は、ただ病気を治すだけでなく、生活に寄り添い、ちょっとしたことでも気軽に相談できる存在であるべきだと考えています。
実際、診察中には「昨日ラーメン食べたんですよ」なんていう世間話も交じることがあります。ある患者様が検査に来られたとき、中性脂肪の数値が極端に高かったので驚いたのですが、後から聞いたら検査前にこってりラーメンを食べた直後だったそうで(笑)。空腹時に再検査してみたら正常値に戻っていて、安心したというエピソードがありました。そうしたやりとりができる関係性があるからこそ、患者様も体調の変化や心配ごとを打ち明けやすくなり、早期発見や予防にもつながると感じています。
医師と患者という立場はあっても、気軽に相談できる“近さ”は大切です。家族や友人とは違う、けれども安心して話せる存在。そんな存在でありたいという想いを持って、日々診療にあたっています。
生活習慣病へのアプローチ
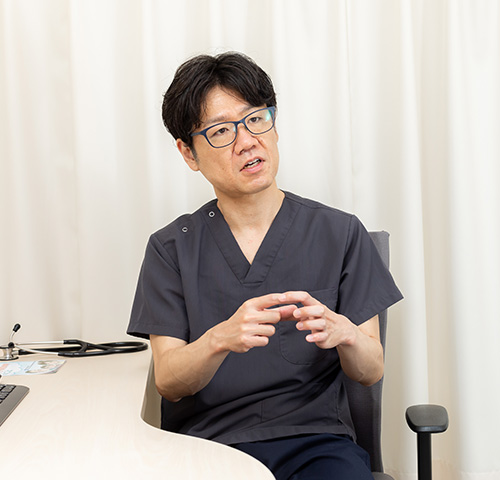
生活習慣病を診る上で心がけていることや、診療方針について教えてください。
生活習慣病というのは、その名の通り「日々の習慣」に深く関わっている病気です。自覚症状がほとんどないまま進行することが多いため、健康診断や何気ない会話の中から気づくことも少なくありません。だからこそ、医師として患者様との対話を大切にし、その方の生活背景や価値観に寄り添った治療方針を考えるようにしています。
たとえば、「飲酒やタバコは控えた方がいい」と一律に言っても、それが患者様の楽しみの一つだった場合、逆にストレスになってしまうことがあります。大切なのは、その方の生活の質を損なわずに、どう折り合いをつけていくか。つまり、医学的に正しいことだけを押し付けるのではなく、「その人に合った現実的な提案」が必要だと感じています。
また、高血圧や糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病は、放置してしまうと将来的に心筋梗塞や脳卒中といった重大な疾患につながるリスクがあります。ただし、年齢やライフステージによって、そのリスクにどう対応するかのバランスも変わってきます。80代の方と60代の方では、治療の強度や目指すゴールが異なるのは当然です。
当院では、そうした一人ひとりの状況に応じて治療方針を調整し、「逃げ切る」医療、つまり長く健康に過ごせるような現実的かつ柔軟な医療を提供することを心がけています。
検査・予防の重要性

健康診断で再検査となった方への対応や、予防医療に対する考え方を教えてください。
健康診断で「要再検査」と言われても、実際にはそのまま放置してしまう方が少なくありません。忙しさや「今は困っていないから大丈夫だろう」という心理が働いて、受診を先延ばしにしてしまうのです。しかし、生活習慣病の怖いところは、まさに「今は何ともない」まま静かに進行する点にあります。
健康診断で示される基準値は、病気の兆候を早期に拾い上げるために、やや厳しめに設定されていることもあります。そのため、「引っかかった=即治療」というわけではありません。当院では、まずは再検査で数値の変動や体調の変化を確認し、そのうえで必要な治療や生活指導を一緒に考えていくというスタンスをとっています。
過去には、血圧が高いと何年も言われながら何もせずにいた方が、ある日突然脳出血で倒れて救急搬送されたというケースもありました。生活習慣病は、症状がない間は軽視されがちですが、積み重ねが大きな結果に結びつくこともあるのです。
「予防」は決して堅苦しいものではなく、むしろ将来の自分のためへの投資です。体調が良いうちにこそ、小さな違和感に耳を傾け、気軽に相談に来ていただけたらと思っています。何かあってからではなく、何か起こる前に。日常の中に“予防”という意識を少しでも取り入れていただくことが、健康な未来につながっていきます。
睡眠時無呼吸症候群と診療の工夫

無呼吸症候群の診療での取り組みや、患者様へのサポート体制について教えてください。
睡眠時無呼吸症候群は、自覚症状が乏しいうえに発見が遅れがちな疾患です。「日中の眠気が強い」「朝起きたときに頭が重い」といった日常のちょっとした不調が、そのサインである場合も少なくありません。特に一人暮らしの方などは、いびきや無呼吸といった症状に気づきにくいため、予防啓発と気づきのきっかけ作りがとても重要だと考えています。
当院では、簡易検査と精密検査の2種類の検査方法を用意しています。以前は入院が必要だった精密検査も、最近では自宅でできる機器が登場しており、検査のハードルがぐっと下がりました。忙しい方や遠方にお住まいの方でも気軽に受けていただけるよう、ご自宅に機器を直接配送したりするなどして、柔軟に対応しています。
治療に関しては、CPAP(持続陽圧呼吸療法)を使った管理が中心になりますが、これは長期的な取り組みとなるため、どうしても途中でモチベーションが下がってしまう方も少なくありません。そういったときには、実際の検査データを一緒に見ながら「これだけ無呼吸の回数が減っていますよ」と具体的な成果を共有するようにしています。また、治療を継続することで高血圧が改善し、薬が不要になるケースもあり、こうしたポジティブな変化を患者様と一緒に実感していくことが大切だと感じています。
治療は「医師から与えられるもの」ではなく、「患者様と一緒に取り組むもの」。その姿勢を大切にしながら、継続しやすいサポートを心がけています。
身近で相談しやすいクリニックを目指して

クリニックづくりやスタッフとのチーム医療で意識していることは?
クリニックは、ただ病気を診る場所ではなく、「ちょっと話を聞いてほしい」「最近調子が気になる」と思ったときに立ち寄れる、そんな安心できる場でありたいと考えています。そのためには、院内の雰囲気づくりやスタッフの声かけもとても大切な要素です。
現在は、受付スタッフ2名と看護師数名の体制で診療していますが、私自身も時間が許す限り、患者様の話に耳を傾けるようにしています。診察室ではもちろん、受付や待合室でも、スタッフが自然に患者様の体調や生活の変化に気づけるよう、日ごろからコミュニケーションを大事にしています。
また、患者様を注意したり叱ったりすることは基本的にしません。健康に関しては、できていないことよりも「できたこと」「少しでも頑張ったこと」に目を向けて、それを一緒に喜び、励ますことが大切だと思っています。たとえば「1日5分でも運動した」ことは、それまで何もしていなかった状態から大きな前進です。そういった小さな一歩をしっかり評価し、言葉にして伝えることが、継続の力になります。
「病院は体調が悪くなったときにだけ行く場所」ではなく、「先生とちょっと話して元気になれた」「ここに来ると安心する」そんな風に感じていただけるような、地域に根ざしたクリニックでありたいと思っています。
最後に読者へのメッセージ
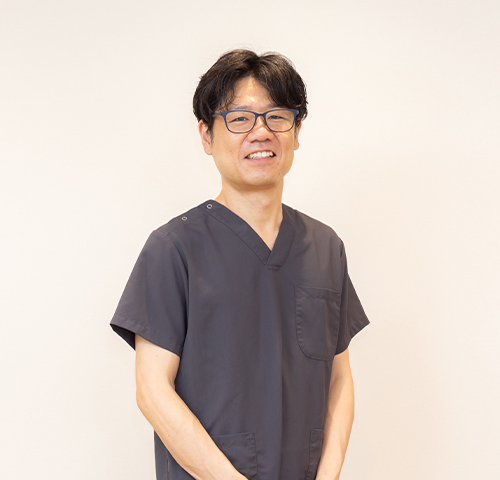
生活習慣病や睡眠に不安を持つ方へ、一言お願いします。
体調や健康について、「ちょっと気になるけれど、病院に行くほどでもないかな」と思うことは誰にでもあると思います。でも、その“ちょっとした不安”を放っておくことで、思わぬ病気につながることもあります。だからこそ、当院では「相談だけでも大歓迎」というスタンスで診療を行っています。
「最近少し疲れやすい」「よく眠れていない気がする」「健康診断で再検査になったけど、そのままにしている」などのちょっとしたお悩みはありませんか?そんなときこそ、ぜひお気軽にご相談ください。
私は、患者様に何かを一方的に押し付けるのではなく、今の状態でできることや、無理のない続け方を一緒に考える診療を心がけています。生活習慣病や睡眠の問題は、決して特別な人だけのものではありません。誰にでも起こり得る、だからこそ“身近な医療”として、当院を皆様のお守りのように思っていただけたら嬉しいです。ちょっと顔を見に行こうかな、くらいの気持ちで構いません。何かあれば、いつでも相談できる場所として、皆さんの健康をサポートしていきたいと思っています。